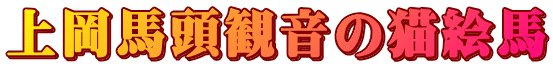 暫定版
暫定版
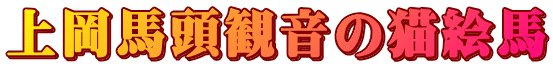 暫定版
暫定版
手描き絵馬
種類:絵馬
制作地:
現制作者:東松山絵馬市保存会
1998年に国の無形民俗文化財に指定されているが保護団体名は特定せず。すでにしてされた時点で絵馬講は解散していたため。
所在地:上岡馬頭観世音 埼玉県東松山市岡1729 慈雲山妙安寺
※東松山市内には田木にも妙安寺があるが、こちらは常祐山 妙安寺で日蓮宗の寺院
慈雲山妙安寺
曹洞宗の寺院。約800年前に瑞慶和尚によって開祖されたと伝えられる。本尊は瑞慶和尚によるものとされ、その中には黄金の尊像が納められているという。馬頭観音は軍馬の守り観音、農家の馬の守り観音として多くの信仰を集めた。400年ほど前の元禄年間に上岡観世音・諏訪神社を管理するかたちで「諏訪山
妙安寺」が建立された。明治期の神仏分離により諏訪神社が離れて山号を改め「慈雲山 妙安寺」となった。現在は妙安寺と観音堂の境内は寸断されてしまっている。
上岡馬頭観世音の本尊御開帳は12年に一度、午年におこなわれる。次は2026年(令和8年)になるが御開帳は3月29日と絵馬市の後になる。月の縁日(19日)には本尊拝登が可能なようで翌2027年の2月19日の例大祭大祈祷会(絵馬市)まで開帳予定だという。
招き猫柄の絵馬はよくある。しかし残念ながら現在はほとんどが印刷になってしまった。古い小絵馬では手描きで奉納されたものも多くある。
上岡観(世)音で毎年2月19日に開催される絵馬市には手描き絵馬が出品される。今回招き猫の絵馬としては初めて招き猫・猫図鑑で取り上げた。
ここの絵馬は岐阜のNさんのインスタグラムで知った。2025年に訪問して招き猫の絵馬を購入した。この訪問については「寒風の中、馬頭観音絵馬市に行く」で報告した。当日の様子はそちらを見ていただくことにして今回は絵馬市の歴史や裏事情に関して記録することにした。
| 慈雲山妙安寺 上岡馬頭観世音 |
 |
 |
| 妙安寺の境内にある観音堂に上岡馬頭観世音が祀られている |
上岡観音の絵馬市について知ったのは最近で、訪問したのもまだ今回(2025)1回のみである。すでに何回も参加されている方には既知のことであるかもしれないが絵馬市に関して記しておく。これに関しては三津山智香(2025)の報告が多いに参考となった。調査報告書としては東松山上岡観音の絵馬市の習俗(東松山市教育委員会、2001)が詳しいようだがなかなか入手が難しくまだ未読である。
三津山智香(2025)は2019年の絵馬市での調査・聞き取りが中心になっているので、比較的情報が新しい。さらにサブタイトルにもあるように「”昔からのしきたり”からの変化に着目して」という点で現在頒布されている多様な絵馬につながっている点が紹介されている点が興味深い。
埼玉県東松山市の妙安寺の境内にある観音堂周辺では毎年2月19日に絵馬市が開催されている。この市には近隣の都県からも多くの購入者が訪れる。絵馬市の始まりは定かではないが絵馬講はすでに明治初年には存在していた。初期の頃は近隣の人々によって経木に神馬の画を描いて境内で売っていたという。やがて経木から丈夫な板へ変わり、絵馬を厩や家に掲げて御利益を求めた。だんだん絵馬を求める人が多くなり、妙安寺と絵馬販売者が相談をして絵馬を販売する組織である絵馬講が結成された。講は全体を取り仕切る帳元のの下に世話人、さらにその下に講員がいた。帳元は世襲であった。講員は問屋(絵馬師)と絵馬を売る売り子に分かれていた。講員は一定の金額を納めて販売権を得て絵馬市終了後に配当金をもらっていた。絵馬講に関する最も古い記録は明治8年(1875)であるという。戦前から昭和30年代初期にかけては100軒ほどの絵馬を売る店が並んだという。しかし絵馬の購入者の減少に伴い昭和63年(1988)が絵馬講としての最後の出店となってしまった。やがて平成3年(1991)に絵馬講自体も解散となってしまった。
講の解散後は絵馬市保存会が結成され絵馬市は続けられた。しかし絵馬市への出店も保存会の1軒のみとなってしまった。
「上岡馬頭観音の絵馬市」は平成10年(1998)に国指定の無形民俗文化財に登録された。しかしすでに絵馬講は解散していたので保存会と東松山市は絵馬市を活性化させる活動を始めた。その際に「むかしからのしきたりを踏襲してやるように」いわれていたが、そのままでは活動が難しいので「昔からのしきたりを踏襲しつつ、どのように絵馬市を変化させていくか」と工夫を凝らしながら現在に至っている。絵馬市を継続していくのが目的なので現在は配当金はないという。
かつては牛馬が農耕や運搬に多く用いられていたため、絵馬市には牛馬飼育者、運送業者や家畜商などが多く参拝していた。
昭和38年(1963)までは馬と牛のみの絵馬が販売されたいた。そこに豚、耕運機、ウサギが追加された。ウサギは売れ行きがよくなくやがてなくなった。鶏の絵馬も一時制作されたという。
2000年代に入り絵馬師が途絶えてしまった。全国で絵馬師を探した結果、2019年の時点で上岡馬頭観音の絵馬に画風が近い男女各一名の絵馬師が描いているという。女性の絵馬師はかつての絵馬を模して描いているので昔の画風に近いという。男性の絵馬師は自身で木も調達し独自の画風であるという。絵柄は保存会の会長が指示しているという。
保存会の時代になり画題もいろいろと変化している。平成28年(2016)ころにはファッション性をもったピンクの毛色の馬「メルヘン」が誕生した。さらに平成31年(2019)の時点で畜産以外のペットの絵馬も販売可能か妙安寺関係者と相談したという。その結果、現在では猫の絵馬が2023年の時点で販売されている。犬の絵馬も販売された。犬の場合は描く犬種が難しそうである。さらに干支の絵馬も制作されているがまだ一巡はしていないようだ。
上岡馬頭観音の絵馬は手描きではあるがすべてを手で描くのではなく、渋紙の型抜きの版を重ね、そこに手描きで細部を描き入れることによって制作されていた。現在では渋紙の代わりに樹脂製の型紙が使用されている。馬は前足を上げているハネで運搬用、足をそろえて立っているタチは農耕用の馬を表現しているようである。モミの木の板に胡粉を塗り、型抜きの版による刷り込みで版を重ね、そこに樫の木で作ったスタンプ状の花形を入れたり、手書きで細部を書き込んでいく。最後に鳥居に見立てた枠を貼り付けて絵馬が完成する。下地の胡粉塗りが省略されていることもある。
絵馬は小型の6寸と大型の尺2寸がある。尺2寸は7頭立てで左から青毛 鹿毛(かげ) 栗毛 黒鹿毛 青とも 栃栗毛 足(芦)毛の順で描かれている。
絵馬や絵馬市に関しては下記の東松山市教育委員会が制作した動画「上岡観音の絵馬市」(2001)が詳しい。おそらく2001年の報告書の作成と同時に制作されたと思われる。
岐阜のNさんのインスタでは2025年には鶏(鳥インフルで多くの鶏が殺処分されたため治まることを祈念して)や雀の絵馬も見られる。同じく2024年のインスタグラムではペットの犬の絵馬もあった。まだ猫(招き猫)の絵馬は頒布されて日が浅いのでこの一種のようである。犬に関しては今年犬張り子の犬が確認できた。
 |
昔ながらに立てかけた戸板の上に並ぶ 尺2寸の大型絵馬 左から青毛、鹿毛(かげ)、栗毛、黒鹿毛、 青とも、栃栗毛、足(芦)毛の順で並ぶ 馬の毛色 (JRA サラブレッド講座 毛色の種類) 馬の毛色と特徴 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル |
| 招き猫絵馬 | |
 |
下地の胡粉塗りはない 型抜きの版を重ね、 そこに手描きで細部を 描き入れることによって 制作されている |
 |
白猫が基調の 黄色の縁取りがある三毛猫 首玉と前垂れを付け、 左前足で招く 黒い尻尾は福を引っかけるという鍵尻尾になっている 左右と上部の黒い枠は 鳥居を表している |
| 猫はおそらく2023年の絵馬市で初めて出たようだ |
 |
手前の白背景が男性の絵馬師 左の絵馬が女性の絵馬師の 作品のようだ |
 |
耕運機やトラクターの絵馬も 最近復活したものらしい 何種類かあるようだ 牛もホルスタイン以外に 黒毛があり、雄牛や雌牛がある |
ねこれくと内の関連ページ
「寒風の中、馬頭観音絵馬市に行く」
上岡観音の絵馬市 制作:東松山市教育委員会 撮影編集平成13年(2001) 約35分 ![]()
曹洞宗慈雲山妙安寺 上岡馬頭観世音HP
みやげもんコレクション248 上岡馬頭観音の絵馬 (ブルータス マガジンハウス 2017)
東松山上岡観音の絵馬市の習俗 (文化庁)
馬体安全祈願、新しくも古式に則った試み (Pen_Saloon ブログ)
参考文献
さいたまの職人 民俗工芸実演公開の記録・第1回~70回(埼玉県立民俗文化センター、1991 埼玉県立民俗文化センター)
民俗工芸収蔵資料解説目録Ⅰ際物(埼玉県立民俗文化センター、1995 埼玉県立民俗文化センター)
埼玉の大絵馬小絵馬(大久根茂、2024 関東図書 さきたま出版会)
絵馬巡礼と俗信の研究(召田大定、1967 慶文堂書店)
調査報告 埼玉県東松山市上岡馬頭観音の絵馬市の現状(三津山智香、2025 歴史人類・筑波大学歴史人類学系)
文化庁月報平成11年2月号no.365(文化庁、1999 ((株)ぎょうせい)
「東松山上岡観音の絵馬市の習俗」 調査・記録作成事業報告書(東松山市教育委員会、2001) 未読
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()