@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@
 @
@
@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @
@
| QOPWNSPQúÁMAQOQPNTPXúÁMC³ QOQSNVTúÁMC³A@QOQTNTPVúÁM |
ºì´yl`EEEºì´Ä«iµ½©íçâ«j
@íÞFyl`
@§ìnFÂX§OOsj[ì
@»§ìÒFJqñiVãÚj
@@@@@@@@¢Û³uiPXUV|@@jQOOPN©çj[ìÅuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Ä¢½J´¡Étµ§ìðnßéB
@@@@@@@@ºì´yl`»©@uºì´Ä°RvÆ éÌÍJ°¡iÜãÚ@°RÍëj
| ã | JàåU | @@@@@@|PWVQN | @@@@@|¾¡TN |
| ñã | J༠| @@@@@@|PWXXN | @@@@@|¾¡RQN |
| Oã | J´Z | @@@@@@|PXPWN | @@@@@|å³VN |
| lã | J¿¾Y | @@@@@@|PXUVN | @@@@@|ºaSQN |
| Üã | J[¡ | PXPXN|PXXXN | å³WN|½¬PPN |
| Zã | ûüJMv | PXTQN|QOPUN | ºaQVN|½¬QWN |
| µã | Jqñ | PXTSN| | ºaQXN| |
@JTgÍà¼Ìí
@¾cH¡YEEE¾cv¾Yi¾cH¡YÌqAJàåUÌÈÌ
Ìqj @@¾cv¾YE¾cH¡YiÂX§§½yÙ@ºì´l`j ¼Éà½_© è
@³R~¾Yi¾cv¾YÌoÌ·jj
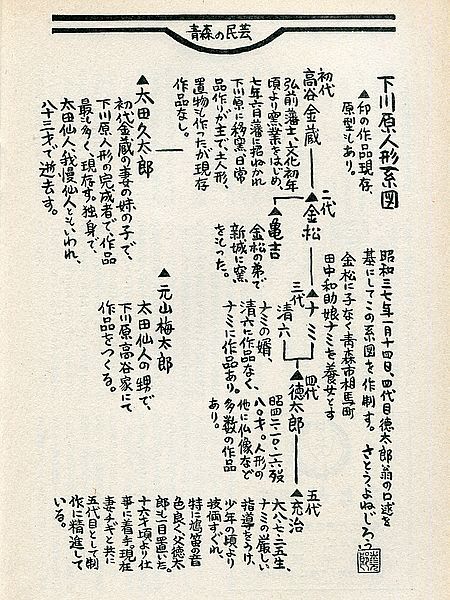 |
ÂXNOWÆ¢¤ÂXåwoÅǪoµÄ¢½nûÉ ÂX§¶¶wïÌk²îƲ¡ÄYª u½yßïºì´l`vÆ¢¤LðfÚµÄ¢é ±ÌɺaRVNiPXUQjÉlãÚ¿¾YÌûqð îɵÄn}ðì¬µÄ¢é ±êÉæèJÆÌyl`ìè̬ꪩ¦Ä«½ ÂXNOWÉfÚ³êÄ¢½²¡ÄYÌÅæÉÍ JTgâ¾càåU̼à©ó¯çêé |
||
ÂXNOW@SæèiãEEj |
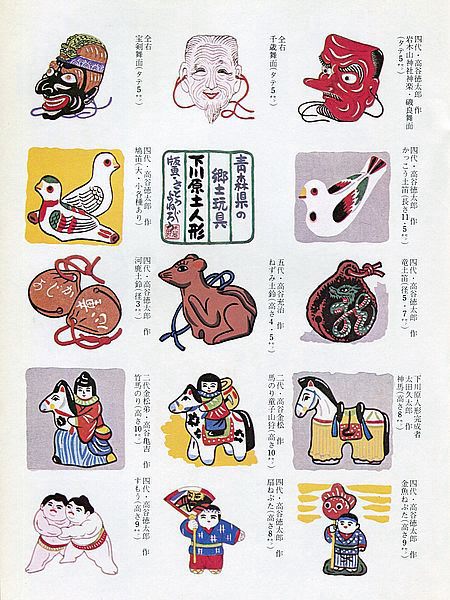 |
||
|
|||
@
 |
UãÚJMv³ñiPXTQ|QOPUj QOORNìÐÈs |
@ÂXNOWSiPXVQjÉæêÎAV¾iPVWP`PVWXj̱ëºì´¡òÉêlÌsÒªað¾ÄZµÄ¢½Æ¢¤B»ÌsҪĨ̼lÅ Á½½ß¾cH¡Yª³¦ðó¯ÎìºåòÉ
@ȨA¾cH¡YÌq̾cv¾YÍìià½c³êAºì´l`Ì®¬ÒÅà éÆ̱ÆÅ éB
@ãJàåUÍá¢Æ«É}OÅ©|ðwÑAÂXÉAÁÄqðJ«A~áú̶ÆƵ½B¶»VNiPWPOjÃyËåÌÃyJeªËÌYÆU»Ì½ßAà ðºì´ÉÄÑñ¹©íìèð§ãµ½B»ÌãAà¼iQãÚjÌãÅ»©ÍúüµúpGíÆyl`ÉêOµ½Æ¢¤Bà¼ÌíTgàqðìèl`ðÄ¢½ª¾¡RQ`RN kC¹ÉnÁ½Bà¼ÉÍqÇઢȩÁ½ÌÅ{ƵÄi~ð}¦»ÌvÌ´ZªRãÚðp¢¾B´ZiRãÚjÉìiÍcÁĨç¸Ai~ÌìiªcÁÄ¢éÆ¢¤B»ÌqÌ¿¾YiSãÚjªãðp¢¾B³çÉPXXXNRÉSÈçê½[¡iTãÚjªãðp¢¾B[¡Íi~©çw±ðó¯ṈëæèZÊÉDêÄ¢½Æ¢¤BÈÌ`MƤɧìÉãñ¾B[¡ÆÀsµÄqÌMviUãÚjª§ìð±¯Ä¢½ª»ÌMvàQOPUNTÉSÈÁ½B»ÝÍíÌJqñªVãÚðp¢Å¢éB
@ÂXNOWÌLqÆÍãàåUª}OÉ»©ðwÑÉsÁ½©A©Hðµ¢½©Ìá¢Í éªÙÚ±êÜÅ̲×ÆêvµÄ¢éBºì´yl`ÌqÍ»Ì}OÌe¿Æ¢íêéB
@ºì´yl`͵JªL¼Åå^ÌàÌà§ì³êÄ¢½B»êÈOÌyl`ÍärI¬^Ììiª½Al`JÉÈÁÄ¢éàÌརB»êÈOÉñl`âDÊqÈÇà§ìµÄ¢½B
@^Í©ÈèâàÌàcÁĨèA¿¾YÌãÉnçê½àÌརƢ¤BܽßNÉÈÁÄ[¡âMvÌãÉÈÁÄàVµ¢^ª¶ÜêÄ¢éB
@A©FAÎA
FÈÇÆÁÌF颪 éB
@»Ý͵ãÚJqñÉæè µÄ¢éâ^Å Üè§ì³êĢȩÁ½l`iJjཧì³êÄ¢éæ¤ÈÌÅ¡ãÌ®üÉúÒµ½¢B
@ȨAJqñÆÌß×Åuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Äºì´Äl`ð§ìµÄ¢éJ°¡iÜãÚjÍeÊÖWÉ éÆvíêéªÚ×Ís¾Å éB
@»ÝÍuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Ä¢½q³ÌJ´¡iëF°RjÉtµ½¢Û³uà§ìð¨±ÈÁÄ¢éB
@µ¢Ä¢È¢©nɽÊíÌÀèLÍärIⶣi½Æ¦Îú{½yßï@ÌjÈÇÉཀྵçêéB±êÍßNÌìiQÌÉÍ©©¯È¢B»Ýà§ì³êÄ¢éâø«Làéç é^Ìæ¤Å éB
@ìèòul`´¶Éf[^x[XvãÉÍÌQ_ÌL^ª éB
@@@@@@ÀèL@@@@@LWx
@ȨAûüJqñÉæè³ê½uLWxvÉÖµÄÍêÔºÅæèã°½ÌÅ»¿çð²¾³¢B
@@@@@@@@
@¡ñÐîµÄ¢éLÍêð«·×ÄJ[¡ é¢ÍMvÌìÅ éB
 |
| »Ýµ«LͱÌSíÞ é |
| Àèeqµ«L | |
 |
 |
| ÀèLÌãɵ«eL | ºì´ÌT^IÈÊF |
 |
 |
| ØÈOê | eq¤É¶è° |
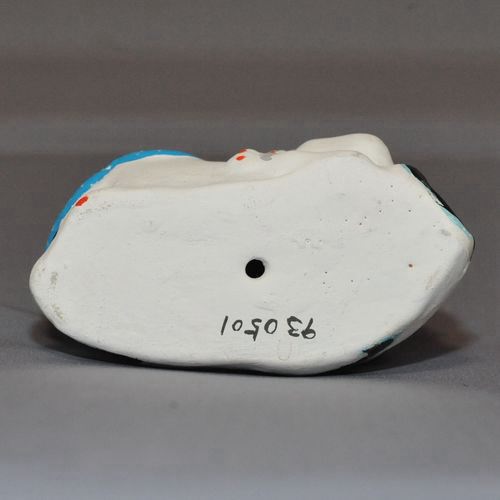 |
³POPmm~¡XUmm~sTPmm µ«LÌÅÍ¢¿Îñå«¢ eLÌã뫪ÈñÆà¤çµ¢|[YðÆÁÄ¢é eq¤É¶è° g¢ñ½ÜÉØÈOê ÌÁÉ FÌæè yJÉÍÈÁĢȢ |
| yJÉÍÈÁĨç¸AêÜÅÓ²ªhÁÄ é |
| eqµ«L | |
 |
 |
| eqµ«L | ¶è°@eLQCà¶è° |
 |
 |
 |
³VUmm~¡SOmm~sSRmm eqµ«Ål`JÉÈÁÄ¢é eÆ¢eLͶè°A Ô¿ÌqLͼèã°ÉÈÁÄ¢é ÎÌñ½ÜÉÔ¢Oê |
| ÎÌRÌ¢½Ô¢Oê |
| µ«L | |
 |
 |
| ÁȵÌL | ¶è° |
 |
 |
| ÎÌRÌ¢½ØOê | Kö̪ª«ûÉÈÁÄ¢é |
 |
³VTmm~¡RTmm~sSOmm ¢¿ÎñI[\hbNXÈ^Cv̵«L ±êàl`JÉÈÁÄ¢é ÁÍÈL |
| êÍhÁĢȢ |
| À赫L | |
 |
 |
| eqµ«LƯlÉã뫪±¿çðü¢Ä¢é | ¢ÁÉ FÌæè@Köà¯ÊF |
 |
 |
| ÎÌRÌ¢½Ô¢OêÉ©FÌé | «û |
 |
³SVmm~¡TTmm~sSRmm ª´yl`Éà éæ¤È¡Àè^Cv̵«L ±êàl`JÉÈÁÄ¢é ¶èã°ÌÁL |
| êÍhÁĢȢ |
@òÌm³ñªºì´yl`Ìq³ðKâµ½ÛÌæÉCÉÈéLªÊÁÄ¢½Beqµ«ÌãëÉBêĵÜÁÄ¢éªÀèLŵ¢Ä¢È¢Bµ©à¨ÍÅÊF³êÄ¢éB±Ìæ¤È¡ÀèLÍc¬µÄ¢È©Á½Bµ«L\ªÔ³ñÌuµ«LPPTÌQvÉÍTCYá¢Ì¡À赫LªfÚ³êĢ骱êæèå«¢BÀèeqµ«LÌh¶^Cv¾ë¤©HÚתCÉÈéB
| âø«L | |
 |
 |
| §¿ãªÁÄâðø«ã°é | ¢ÁÉÌæè |
 |
 |
| ©F¢ªÉæÁÄ¢éªA½¾ë¤©H | µ¢Ä¢éæ¤É੦éEè |
 |
³UPmm~¡SOmm~sRTmm Ì©ç é^ g¢âðø«ã°Ä¢é ±Ì^CvÌâø«Í@@ÈÇíÞª½¢ Lª½©ÉæÁÄ¢éæ¤É©¦éª ½ÉæÁÄ¢é©Ís¾ Ô¢RÉÎÌOê |
| êÍhÁĢȢ |
| ÀèL | |
 |
 |
| Àè | ÁȵÌL |
 |
 |
| ÎÌRÉÔ¢Oê | «û |
 |
³QQmm~¡RTmm~sRUmm ¬^ÌÀèL^CvÌyJ ÁȵÌL ÎÌRÉÔ¢Oê |
| êÍhÁĢȢ | |
 |
 |
| âí¦L | |
 |
 |
| å«ÈâðûÉø¦Ä | O«Åâð³¦Ä¢é |
 |
 |
| ãë«ÍOÌûÉ èͪüÁÄ¢é | «û |
 |
³QPmm~¡RUmm~sTQmm ÁÌL ÁÉÍæèȵ å«Èâðø¦ÄO«Å³¦Ä¢é |
| êÍhÁĢȢ | |
 |
 |
ßÌL^©ç
@µ«LÌ É©ê½wüútðÝéÆPXXRNTPúÆ èÜ·B±ÌúOOsÌTãÚJ[¡i¶ã¤¶j³ñÌH[ðKËܵ½BJ[¡³ñÍå³WNiPXPXj¶ÜêÅK˽ÍVOã¼Îŵ½Bu©w³¹Ä¾³¢vÆ¢¤ÆuǤ¼vÌê¾¾¯Å^â^²«ªIíÁÄÊFðÒÂyl`Å¢ÁÏ¢ÌìÆêÅÙXƧìð±¯Ä¢Üµ½BܳɨéÈEl³ñÌT^IÈûŵ½Buµ«LÌÝÉÍ èÜ·©vÆqËéÆAu¡±±ÉÍÈ¢ªÂXsŧqªW¦¦ðâÁÄ¢évÆ̱Æŵ½B§q³ñª[¡³ñÆ¢ÁµåɧìÌ©½íçAW¦ïÈÇðâÁÄ¢éæ¤Å·B»ÌãA[¡³ñÆÍÄï·é±ÆÈA½¬PPNiPXXXjRQRúÉVXÎÅSÈçêܵ½B[¡³ñªSÈçê½ãÍÂXÅW¦¦ð³êÄ¢½ZãÚÌMv³ñªãðp¬AÈOÆÏíçÈ¢pźì´Ä«Íìç걯ĨèAºì´yl`ÍÀ×Ìæ¤Å·B@@=OEO=
| JMv @µJiÍÆÔ¦jÈÇÅmçêAOOsÉËã©ç`íéuºì´ÄvÌUãÚq³EJMvi½©âEÌÔ¨j³ñªQOPUNTSúßãXRRªAݪñ̽ߧa@@\OOa@ŵ½BUSÎB @J³ñÍQTΩçºì´Äyl`ìèÉÅ¿ÝAQOOQNÉͧ`H|mÉFè³ê½BJ³ñªè|¯éDµ¢\îÌìiÍALlCðWß½B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QOPUNTVú@¤Vñ@æèÒW @ȨA»ÝµãÚÆÈÁÄ¢éÌÍíÌJqñiÆà¶j³ñB @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
æݪ¦Á½uLWxv
@uLWxv;¡ãɬsÁ½[Su¨Á¿å±¿å¢ßvÌuLÀáLÀáƨÁµá¢Ü·ªALªñ¢ÄièÌßÅéàÌ©vð³ÉµÄ¢éàÌÆvíêéBºÐ^ª êεÄà碽¢¨àµë¢àÌÅ éB
@¬ÑõêYÌwuxè̤LÌbvÉ̪gÝÜê½wixÉæêÎOOÉà±ÌLWxÌ`³ª éÆ¢¤B
@ãLÌæ¤ÉÈO¢½uLWxv¾Á½ªAÅßÉÈÁÄòÌuLWxvðͶßÆ·édöV[YªVãÚJqñÉæè§ì³êÄ¢é±ÆðmÁ½B
@@@@@@@@@Üé²ÆÂX@]Ëã©çÌdö¶»ªNâ©ÉhéIµãÚqñ³ñÌdöV[Y©çJºì´Äyl`»©
@±ÌLÉæêÎAuðMJvAuÜJvAu¥JvAuçJvAu·è«JvAu©Ú¿áJvÍñãÚJ༪^ðìÁ½àÌB
uUJvÍà¼ÌíATgª^ðìÁ½àÌBuREJvAÍu»¯LJvÍãàåUÌA¾cv¾Yª^ðìÁ½àÌB»êÉlãÚ¿¾Yª^ðìÁ½uͶJvÌPP_ªdöV[YÆµÄ é椾BdöÌíÞƵÄÍSSésÉoê·éùïÌÞª½¢B
ìèòÌ`¢½uååP̨»¯vªuREJvÉ ½éBuLWxvÍu»¯LJvÉ ½éB
@l`ÌÚ×ÍãÌuÜé²ÆÂXvðQƳ꽢B
@Üé²ÆÂXvÉfÚ³êÄ¢éuLWxvi»¯LjÍìèòª`¢½ìiÆÍÊFªÙÈÁ½BÔMnKLðüêÄâ¢í¹½Ì¾ª¡ÌƱëÔMÍÈ¢BòÌN³ñª¼ÚH[ðKâµÄòÌÊFŧìð˵Ģ½ìiªÅ« ªÁ½æ¤ÅAêÌ¢½¾¢ÄµÜÁ½B»êªºÌæÌLÅ éB
@ìèòÌl`´¶ÉÌLWxÆ döV[YÌu»¯LvðärµÄ¢½¾Æ¨àµë¢B
@ȨAdöV[YÌuREJvÍãLÌæ¤ÉìèòÌ`¢½uååP̨»¯vÉ ½èA±êàLÆvíêéBUJÍ«Â˾뤩H
| LWxi»¯Lj | |||
 |
 |
||
| ¨É¿ªüé | ¨âèÊ®¢ÌFªÙÈé | ||
 |
 |
||
| è«Ìæ[ÈÇ×ÌÊFªÙÈé | yJÈÌÅ«ûÍÊFȵ | ||
 |
³WUmm~¡SVmm~sRXmm ¨âèÊ®¢ÌFªÙÈé ¨ÉÍTNÌæ¤È¿ªüé èiO«jÉÍÌÁÆܪ`©êé «iãë«jÌÜÍȪ³êÄ¢é èÉÁÄ¢éÌͽŠ뤩H yJÉÈÁÄ¢éÌÅyð¦ßéÆ¢¤±ÆÅ «ûªÍfÄ«ÌÜÜ ^;cv¾Yì @@@@ |
||
| yJÉÈÁÄ¢é | |||
|
|||
 |
»Ý§ì³êÄ¢él` Üé²ÆÂX u]Ëã©çÌdö¶»ª @@@@@Nâ©ÉhéIviQOQPjæè EÍÊFÌF`[g |
||
 |
| Yt̵¨è |
@@@@@
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]()
@@@@@yºì´Äyl`zfpÅDµ¢¹FÌÃy`H|@@OOmiÂX§OOsÏõTCgj
@@@@@q`aÂXú@µJÉyl`uOOÌ`H|Eºì´Ävi®æj@iJqñj
@@@@@q`aÂXú@µJÉyl`uOOÌ`H|Eºì´Ävi®æj@iJqñj@ãƯ¶
@@@@@Üé²ÆÂX@ÃyÌl``ºì´Ä`@@iQOOXNÌîñÈÌÅJMv³ñ¶½ÌLÅ·j
@@@@@Üé²ÆÂX@]Ëã©çÌdö¶»ªNâ©ÉhéI@iQOQPDVj
@@@@@
@@@@@l`Ìï¿@ºì´Ä«i¢Û³uj@
@@@@@ÊûƱ®àè @OO@ºì´l`@@iJ°j@
@@@@@ºì´Ä«yl`»©@¶áçñlbg@iJ°j@
Ql¶£
µ«Lsµ@irìçqE°iAPXXX@ÆÅj
ú{½yßï@ÌiäYAPXRO@n½Ð[j
uâÔ@LviéØíYAPXVQ@ÆÅj½yßï}à浪iéØíYAPXWW¢@ºcXj
S½yßïKChPi¨ìhOAPXXQ@wEoÅÐj
¨à¿áÊMQOOi½cÃêAPXXU@S½yßïFÌïßExj
J¿¾Y¥Ìv¢o@Î̤{æ\OWiÎ̤{ÌïAPXUW@OOEÎ̤{Ìïj
½yßï@ElÎȵiâ{êç APXXV@wEoÅÐj
ú{̽yßï@kiâ{êçE¼APXUQ@üpoÅÐj
ÂXNOWSiÂXåwoÅÇAPXVQ@ÂXåwoÅÇj
uxè̤LÌbvÉ̪gÝÜê½wii¬ÑõêYAQOOW@_ÞìåwQP¢ICOEvO¤iïcj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]()
![]()
![]()
![]()
![]() @@@@@@@@
@@@@@@@@![]()
![]()
![]() @@@@
@@@@